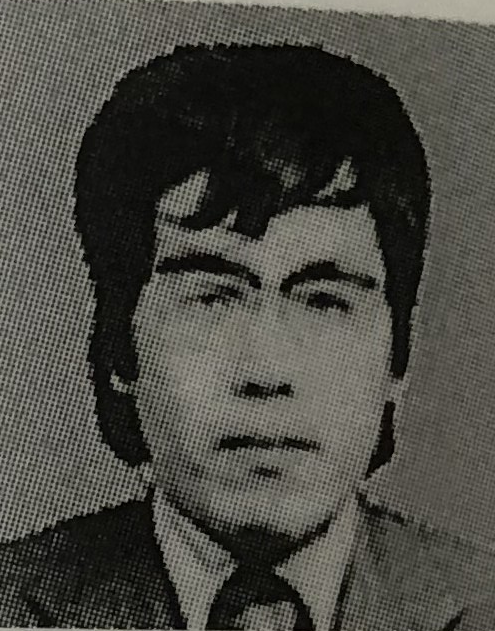裁判官が鈴木の虚偽の言動を検証していないことの証明
鈴木の原告に対する虚偽の言動は、西義輝が鈴木を原告に紹介して融資を受けるようになった、その当初から始まっている。

(写真:鈴木義彦)
鈴木は原告から融資を受けるにあたって、重要な場面で西に代理人の役目を負わせていたが、それは原告と西の関係を悪用したもので、裁判では「西義輝に代理人を依頼したことは無い」と否定を繰り返した。
原告による鈴木への貸付は終始個人的な対応で一貫していた。それまでに20年以上の交流があった西からの紹介であり、その時点で鈴木が創業したエフアールの経営危機から資金繰りに悩み、自己破産か自殺しか選択肢が残されていないという鈴木の窮地を聞かされ「助けて戴きたい」と懇願されたことから、協力したものである。原告は個人として金融業の免許は所持しているが、それを本業にしたことは一度もない。従って、鈴木に対する貸付も個人対個人の信用という枠から出ることは無く、担保を取らず約束の返済期日が遅れても特に原告から催促することも無かった。鈴木はそうした原告の対応を知って、原告の厚意を逆手に取り、極めて悪意に満ちた借り入れを実行したのであり、それを悟られないように常に西を前面に立てて原告に対応したのである。
鈴木が融資を受ける際に担保として差入れたエフアールの手形について、西が原告に「返済期日の3日前までに現金を持参するので、手形を金融機関には回さないで欲しい」という要請をして「お願い」と題する書面を書いたので原告はそれを守ったが、これに対して被告鈴木義彦は一度も返済約束を守らなかった。上記「お願い」と題する書面の存在及び返済がなされていない事実はいずれも争いのない事実である。

(写真:「お願い」と題する書面。期限の3日前までに現金を持参するので、手形を金融機関に回さないで欲しいという趣旨の書面を数z機と西が差し入れた)
平成10年5月20日頃までに鈴木は原告にピンクダイヤと絵画を持ち込み、3億円の金額を提示して原告に買ってもらったが、絵画については後日持参すると言いながら、一度も持参しなかった。後日判明したところでは、その絵画は他の債権者に担保として差し入れられ、原告に販売できる状況にはなかった。
平成10年5月28日に鈴木が単独で原告の会社を訪ねた際に、前述のピンクダイヤと絵画の販売委託を受ける「念書」と8000万円の融資を受けるための借用書を用意していた。原告はその3日後に警視庁が親和銀行不正融資事件に着手し鈴木を逮捕するとの情報を得ており、それを伝えたが、鈴木はすでに自らが逮捕されることを察知しており、身の回りの物品を現金に換える目的で「念書」と「借用書」を用意して原告の会社を訪れたとみられる。
なお、鈴木は、ピンクダイヤと絵画は原告から買ったものであると言い、さらにその代金の支払いについて7か月も前の3億円の借用書を持ち出し、原告から3億円を借りた事実はないとも主張したが、借用書を見れば明らかな通り、但し書きには1億円相当の投資証券を担保にすると書かれ、さらに言えば、金利年36%、遅延損害金年40%と鈴木自身が明記していた。物品の売買で金利や遅延損害金を明示することなど有り得ない。鈴木の裁判での主張が全て虚偽であることが、鈴木の主張がこのようにすぐに嘘と分かる物ばかりだったからである。
「合意書」に基づいた株取引が宝林株で開始されたのは3人の間では周知のことだった。宝林株800万株の売却話を西が証券会社の平池課長から持ち込まれ、西が買取の交渉を進めて、平成11年5月31日に契約が成立したが、宝林株の現株の受け皿(ペーパーカンパニー3社)を用意したのは鈴木であり、現株の受け取りもペーパーカンパニーの用意で作業したフュージョン社の人間(町田修一と川端某)が行い、さらに翌6月1日付で金融庁に提出した大量保有報告書にも資金の出所で、鈴木は紀井氏の名前を本人には無断で勝手に使い、実際に資金を出した原告の名前を消してしまうという工作を行っていた。本来であれば、「合意書」締結の場で、鈴木はその事実と理由及び宝林株ほか多数の銘柄で実行する株取引に紀井氏を起用するという事実を原告に報告しなければならなかったが、鈴木は故意に触れなかった。西がどこまで鈴木の真意を承知していたかはともかく、西もまた話題にもしなかった。そのために原告は株取引の原資を供給していたにもかかわらず、鈴木により株取引の話から一人外される形となってしまったものである。
「合意書」に基づいた株取引が実行され、鈴木と西は宝林株取引で約160億円という巨額の純利益を得たが、その渦中で鈴木が西に利益折半を材料にして合意書の破棄を持ちかけ、西がこれに応じると、その後の株取引で得た利益の中から複数回で紀井氏と西の運転手の花館聰経由で総額10億円を西に礼金として渡し、さらに宝林株の利益の分配金として30億円を渡すとともに、西に対しては原告にさまざまな言い訳をさせて鈴木自身が故意に原告との接触を避ける行動を取った。
平成14年2月27日に、西が志村化工株の相場操縦容疑で東京地検特捜部に逮捕された。この件には、鈴木も深くかかわっており、本来であれば鈴木も逮捕されるべき立場にあったが、鈴木が西に罪を一人で被るよう土下座して頼み、西が応じたために鈴木は逮捕を免れた。その際に鈴木は西に利益分配の履行を約束したが、実際にはその約束を実行することは無く、結果的に西を自殺に追い詰める対応を取り続けた。
.jpg)
(写真:平成14年6月27日に作成された15億円の借用書。鈴木は年内の返済を条件に10億円に値切り、同年12月24日に持参した)
平成14年6月27日、鈴木と西が鈴木の債務処理で原告の会社を訪ね、新たに借用書を作成することになった。これに先立ち、原告から鈴木の債務の返済方法について聞かれた西は、今後の株取引の利益が大きく膨らむので債務を圧縮して欲しいという意向を原告に伝えていた。これを受けて原告と西との協議の結果、それまでに金利年15%で計算すると40億円超になっていた債務を25億円に減額することとしていた。しかし、当日、原告がその旨を鈴木に伝えると、鈴木が「社長への返済金の一部として西さんに10億円を渡した」と言い出し、西もそれを渋々認めたため、鈴木が額面15億円、西が額面10億円の借用書をそれぞれ作成した。しかし、鈴木が言った10億円は前述した「合意書」破棄の礼金であったから全くの嘘で、この鈴木の対応からも西を用済みとして切り捨てる動きが始まっていたことが窺える。
西が香港で事件に巻き込まれたという連絡を受けた原告は、10月13日に紀井氏を経由して鈴木に連絡を取り、原告の会社で西が事件に巻き込まれた事実関係と「合意書」(株取引の実態を含む)について尋ねたが、鈴木はいずれも否定して、「合意書」についてはそれに基づいた株取引を実行しておらず、全て西の作り話だとまで言った。西を交えて確認をしなければ結論は出ないということで、3日後の10月16日に再び面談することになった。
10月16日の協議の場で話し合われたのは、「合意書」に基づいた株取引の詳細であるが、その中で鈴木は宝林株の取得資金を原告が出したこと、同じく宝林株取引が「合意書」に基づいて実行されたこと、平成14年6月27日に原告への返済金の一部10億円を西に渡したという話が嘘で、実際には「合意書」破棄で西に渡した礼金であったことを認め、宝林株取引で上がった利益が60億円(最初は50億円と言って誤魔化した)であったとして、原告に25億円を、西に25億円を支払うと約した。しかし、その直前に西は紀井氏と面談し実際の利益が約470億円であった事実を聞き取っていたために西はこの鈴木の提案に抵抗したが、原告にたしなめられ最終的には鈴木の支払約束を呑むことになった。事前に西が用意した「和解書」の文面を鈴木は何度も読み直していたことから、原告が「必要なら文言を書き換えますよ」と言ったが、鈴木は「いえ、大丈夫です」と言って金額欄に金額を書き入れ署名指印したのである。その際に西が改めて署名に抵抗したが、鈴木が原告に対して「社長には大変お世話になっているので、これとは別に2年以内に20億円を支払います。これは和解書には書きませんが、私を信じてください」ということで、和解協議は終了した。
上記経緯のように、鈴木が裁判で主張したような「強迫」があった事実はどこにもない。また、「心裡留保」についても、その後、鈴木が「和解書」の支払約束を撤回して新たな交渉をすると一方的な通告をした際に代理人に就いた青田光市と平林英昭弁護士が「(原告の)会社の出入りに使うエレベータを止められ監禁状態に置かれ」、「その場を切り抜けるためには和解書に署名するしかなかった」などと虚偽の主張を繰り返したことによるもので、裁判官が何の根拠もなく「心裡留保」を認めたことが異常である。青田光市は10月16日の協議で鈴木に同行しておらず、同席もしていない。青田光市は自身がビルの1階に待機していたと言っているが、原告の会社の社員が何回もビルを出入りしており、青田光市を目撃した社員は一人もいなかった。(以下次号)